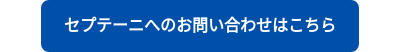API連携とは?仕組みや実装方法、具体例を分かりやすく解説
- AI
Septeni FOCUS 編集部

Webサービスやアプリの開発において、ほかのサービスとスムーズに情報をやり取りするために欠かせないのが「API連携」です。
例えば、地図情報の表示やSNSログイン機能など、私たちが普段使っている多くの機能もAPIを通じて実現されています。
しかし、「API連携って具体的にどんな仕組み?」「どうやって実装するの?」と疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、API連携の基本的な仕組みや実装方法、代表的な活用例まで、初心者にも分かりやすく解説します。
※こちらの記事は2025年7月4日時点の情報です。
API連携とは

APIとは、「Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)」の略で、異なるシステムやサービスが情報や機能を相互に利用できるようにする仕組みです。
このAPIを活用して複数のサービスをつなげ、自動的にデータや機能を連携させることを「API連携」と呼びます。
例えば、勤怠管理システムと給与計算ソフトをAPI連携させれば、出退勤データがリアルタイムで給与計算に反映され、手作業でのデータ入力や転記漏れを防ぎ、業務の正確性とスピードが向上します。
また、ECサイトと在庫管理システムをAPI連携すれば、注文が入るたびに在庫情報が自動更新されるため、売り越しや在庫切れを防ぎ、顧客満足度の向上や販売機会の損失防止にもつながるでしょう。
ほかにも、会計ソフトと銀行口座を連携して入出金データを自動取り込みしたり、LINE公式アカウントと予約システムを連携してチャットボットから予約を受け付けたりと、API連携は私たちの日常生活やビジネスシーンにおいて幅広く活用されています。
API連携の仕組み

API連携は、システム同士が決められたルールに従って「リクエスト(要求)」と「レスポンス(返答)」をやり取りすることで、データや機能を共有します。
例えば、ECサイトが在庫数を知りたいとき、「この商品の在庫は?」というリクエストを在庫管理システムに送信します。すると、在庫管理システムから「在庫は10個です」というレスポンスが返され、画面に反映されるというのがAPI連携の仕組みです。
このやり取りは通常、HTTPという通信プロトコルの規約を利用して行われ、JSONやXMLといった形式で情報を表現します。最近では、特にREST APIと呼ばれる形式が広く使われており、シンプルで扱いやすいのが特徴です。
API連携では、このリクエストとレスポンスのやり取りが瞬時に行われ、システム間でリアルタイムにデータが同期されます。
その結果、手作業による更新や確認作業が不要となり、正確でタイムリーな情報更新ができるようになるのです。
API連携のメリット

API連携を活用することで、企業はさまざまな業務課題を効率的に解決できます。
企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支える重要な仕組みの一つと言えるでしょう。
ここでは、API連携によって得られる主な4つのメリットを紹介します。
業務効率化につながる
複数のシステムをAPIで連携させると、情報の入力や確認、転記といった手作業が不要になります。
例えば、カスタマーサポートツールとCRM(顧客管理システム)をAPI連携すれば、問い合わせを受けた場合に、担当者が顧客の過去の購入履歴や対応履歴をリアルタイムで確認できるようになります。業務効率が向上し、的確なサポートの提供が可能になるでしょう。
さらに、手入力による数量ミスや情報の転記漏れといったトラブルを防げるため、顧客満足度や業務の信頼性が向上することも大きなメリットです。
リアルタイムにデータ共有できる
システム間でのデータのやり取りがリアルタイムで行えるのも、API連携のメリットです。
例えば、POSレジと売上分析ツールをAPI連携すれば、売上情報が即座に分析ツールに反映され、店舗ごとのパフォーマンスをタイムリーに可視化できます。即時性のあるデータ共有は、経営判断のスピードを高めるだけでなく、現場での柔軟な対応にも役立つでしょう。
在庫が急減している商品をリアルタイムに把握し、素早く補充をしたり、売れ筋商品に応じてキャンペーンを即時展開したりと、状況に応じたマーケティング施策を実行しやすくなります。
システムの拡張性が高まる
API連携を活用すれば、既存のシステムに対して新たな外部機能をスムーズに追加することも可能です。ECサイトに決済代行サービスのAPIを組み込めば、クレジットカード払いや電子マネー、後払いなど多様な支払い方法に簡単に対応できるようになります。
ほかにも、チャットボットや自動翻訳APIと連携すれば、カスタマーサポートや多言語対応といった機能の拡張もできるでしょう。
システム全体を作り替える必要がないため、導入のハードルが低く、事業の成長やニーズの変化に迅速に対応できるのがメリットです。
コスト削減につながる
API連携は、業務の自動化と効率化によって人的リソースの最適化を可能にします。
従来のように情報をCSVファイルに入力しての取り込みやバッチ処理によるデータ更新を行う場合、それぞれの仕様に合わせて個別開発やメンテナンスが必要でした。
しかし、API連携を活用すれば、これらの処理を標準化されたインターフェースで一元管理できるようになります。
これにより、開発・運用コストだけでなく、保守にかかる工数やトラブル対応の手間も削減できるでしょう。
また、外部サービスをAPI経由で導入することで、自社で初めからシステムを構築・開発するよりスピーディーかつ低コストで機能の追加が可能です。コストパフォーマンスの高さに加え、開発者のリソースをより生産性の高い業務に集約できるのもメリットの一つです。
API連携のデメリット

API連携は業務効率化やコスト削減に大きく貢献する一方で、導入・運用にあたっては慎重な検討が必要です。
ここからは、API連携を検討する際に押さえておきたい代表的なデメリットを4つ紹介します。
外部サービスへの依存が高まる
API連携では外部サービスの安定稼働を前提として、自社システムの機能を構築するケースが多くなります。そのため、連携先サービスでトラブルや仕様変更が発生した場合、自社の業務にも直接的な影響が及ぶリスクを考慮しなければいけません。
例えば、決済サービスや配送システムなどとAPI連携している場合、それらのAPIが一時停止したりエラーが起こったりすると、受注や出荷のプロセスがストップし、顧客対応や信頼にも影響が出かねません。
このようなリスクに備えるには、API提供元のステータス情報を常に把握できる仕組みを整えることや、フェイルオーバー(代替手段)として複数サービスの並行利用が有効です。
セキュリティ対策が必要
API連携により、社内外のシステム間でデータがやり取りされるため、情報漏えいや不正アクセスのリスクが高まります。
特に、顧客情報や決済情報などの機密データを扱う場合は、堅牢なセキュリティ対策が欠かせません。
代表的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。
-
通信内容を暗号化する(HTTPSの使用)
- APIキーやシークレットキーの安全な管理
- IP制限や認証・認可の導入(OAuth2.0など)
- アクセスログの監視と不正検知ツールの活用
また、API仕様が公開されていることで攻撃の対象にもなりやすいため、最小権限の設計や不要なエンドポイントの無効化といった基本的な対策を徹底しましょう。
運用や管理が複雑化する
API連携を増やせば増やすほど、システム全体の構成が複雑になり、管理の負荷も高まります。
また、複数のAPIが連動する場合、一部の不具合が連鎖的にほかのシステムに影響する可能性もあるため、障害対応が難しくなるでしょう。
例えば、顧客情報の更新がCRM・メール配信・チャットボットにまたがって連携されている場合、1つのAPIに障害が出るだけで一連の処理が止まり、特定の情報だけが更新されないといった不整合が起こる可能性があります。
こうした問題を防ぐには、API連携の構成を可視化した設計書や運用マニュアルを用意し、監視体制やトラブル発生時のエスカレーションルールを明確にしておくことが重要です。
プログラミングの専門知識が必要
API連携の実装には、開発言語・HTTP通信・データ形式(JSONやXMLなど)に関する知識が求められます。
最近では、ZapierやMakeなどのノーコードツールを使って一部のAPI連携を実現することも可能ですが、大規模な連携や細かな制御が必要なケースには対応できないことも多いです。
自社に開発スキルを持つエンジニアがいない場合は、外部の開発会社やフリーランスに依頼することも検討する必要があり、コストがかかる点はデメリットと言えます。
API連携の実装方法

続いては、API連携の具体的な実装の流れについて、4つのステップに分けて解説します。
①連携するAPIを選定
まずは、「どの業務を効率化したいのか」「どんな機能を追加したいのか」といった目的を明確にし、それに合ったAPIを選定します。
例えば、予約受付を自動化したい場合は、予約管理システムやLINE Messaging APIなどが候補になるでしょう。目的に合うAPIが見つかったら、提供元のWebサイトや開発者ポータルで利用条件や仕様を確認しましょう。
APIの利用にはユーザー登録が必要な場合が多く、サービスによっては事前審査や承認プロセスが設けられていることもあるため、導入スケジュールには余裕を持つことが大切です。
②APIキーを取得
APIの利用が承認されると、「APIキー」または「シークレットキー」と呼ばれる認証情報が発行されます。
これは、連携先サービスと自社システムを安全につなぐためのパスワードのようなもので、外部に漏えいすると不正利用のリスクがあるため注意が必要です。
環境変数での管理やアクセス制限の設定など、セキュリティ面に配慮した運用体制を構築しましょう。
③仕様書に従って実装
APIキーを取得したら、API提供元が公開しているAPI仕様書(ドキュメント)をもとに実装していきます。
仕様書には、利用可能なエンドポイント、必要なパラメータ、レスポンス形式(JSONやXMLなど)、認証方法(OAuthなど)が記載されているのが一般的です。
具体的な実装は、利用するプログラミング言語や開発環境によって異なりますが、多くの場合はHTTPリクエストを使ってデータを送信・受信します。最近では、PostmanやSwaggerといったツールを使って事前にAPIの動作確認をしながら開発するケースも増えているようです。
④テスト・デバッグを実施
API連携の実装が完了しても、すぐに本番環境へ移行するのは避け、まずはテスト環境での動作確認を行いましょう。
想定したデータが正しく送受信されるか、異常系のエラー処理が適切に動作するかなどを重点的に検証します。
また、APIの仕様変更やネットワーク障害に備え、エラー発生時の処理(リトライ機能、ログ出力、ユーザーへの通知など)も実装しておくと、安定運用につながります。
API連携の具体的な活用事例

API連携は、業務の効率化やサービス品質の向上を目的に、さまざまな業界・企業で導入が進んでいます。
続いては、実際に行われている活用事例を3つ紹介します。
サイボウズ×Googleカレンダー連携
サイボウズが提供する「kintone」は、ノーコードやローコードで業務アプリを構築できるクラウドサービスです。多くの企業が、社内の案件管理やスケジュール共有に活用しています。
kintoneでは、「Googleカレンダー」とのAPI連携によって、アプリ上で登録した予定を自動的にGoogleカレンダーに同期できるのが特徴です。
例えば、営業担当者が顧客訪問の日程をkintoneで入力すると、その情報が即座にGoogleカレンダーにも反映されます。
これにより二重入力の手間が省け、スケジュールの整合性が保たれるだけでなく、チーム間の情報共有もスムーズになります。
特にテレワークや外出の多い部門において、スケジュール確認がリアルタイムでできる環境は大きなメリットです。
Slack × GitHub連携
ソフトウェア開発の現場では、「Slack」と「GitHub」を組み合わせたAPI連携がよく利用されています。
この連携によって、GitHubでIssues(課題)やpulls(変更提案)が作成されると、Slackの指定チャンネルに自動で通知が送られます。
開発メンバーはSlack上で更新情報をすぐに確認できるため、都度GitHubを開かなくても作業の進捗が把握でき、対応の遅れや確認漏れを防ぐことができるのです。Slack上で簡単なやり取りや確認ができることで、開発チーム内のコミュニケーションが活性化し、作業スピードや品質の向上にもつながります。
LINE公式アカウント×楽天市場の連携
楽天市場に出店しているECショップでは、「LINE公式アカウント」とECシステムをAPIで連携し、購入者への情報配信に活用する事例が増えています。LINE Messaging APIを活用し、商品再入荷通知や新商品情報通知をLINEで自動配信することで、従来のメールに比べて開封率が高く、ユーザーにリアルタイムで情報を届けられるのが大きな特徴です。
また、LINE上でクーポンを発行し、それを楽天ショップで使えるようにすることで、購入後の再訪問や再購入につなげることも可能です。
「楽天お買い物マラソン」や「スーパーセール」といったイベントに合わせた情報配信もスムーズに行え、販促効果を高めることができます。
楽天市場に限らず、ShopifyやBASE、makeshopなどのECプラットフォームでも、LINEとのAPI連携は可能です。
自社ECサイトでも応用できる柔軟性の高さが、LINE活用の魅力と言えるでしょう。
API連携を上手に活用してビジネスの成長を加速させよう

API連携は、業務の効率化やコスト削減につながるだけでなく、リアルタイムなデータ共有による意思決定の迅速化、顧客満足度の向上など、多方面にわたってビジネスの成長を支援する強力な手段です。
販売管理・在庫管理・顧客管理といった業務システムをAPIでつなぐことで、データの一元化が実現し、組織全体での情報活用がスムーズになります。
一方で、API連携の導入には、開発知識やセキュリティ管理、外部サービスへの依存リスクなど、注意したいデメリットも存在します。特に個人情報や決済情報を扱う場合には、セキュリティの堅牢性や通信の暗号化といった基本対策を徹底することが重要になるでしょう。
信頼できるAPIを適切に選定し、運用体制を整えれば、API連携は中小企業でも導入可能なコストパフォーマンスの高い手法です。
「複数の業務ツールを連携させて手間を減らしたい」「新サービスを迅速に展開したい」といった課題を解決するためにも、API連携の導入を積極的に検討してみてはいかがでしょうか。
こちらの関連記事もお読みください。
執筆者

Septeni FOCUS 編集部
「Septeni FOCUS」は、Septeni Japan株式会社が運営するマーケティング担当者のためのメディアです。
カテゴリ
関連するお役立ち資料
関連するお役立ち資料はありません。
関連するウェビナー / アーカイブ動画
-

- セミナー
- 開催日 2026.2.12
AI検索面×AI Max!Google広告のポテンシャルを最大化する方法
-
.jpg?width=380&height=222&name=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC_02a_1628x850_B_250528172200CFM139279%20(2).jpg)
- アーカイブ
- 開催日 2025.6.18
2025 Marketing Summit TikTok for Business & セプテーニ 協業セミナー
-

- アーカイブ
- 開催日 2025.2.19
「AIエージェントで変わるマーケティング最前線」 〜海外最新事例と企業導入・活用のリアル〜
-

- アーカイブ
- 開催日 2024.12.19
AIとLINE公式アカウントで実現する顧客体験の革新
-

- アーカイブ
- 開催日 2024.10.03
Performance Marketing Summit Meta & セプテーニ 協業セミナー