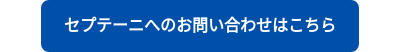生成AIのメリット・デメリットとは?問題点と対策のポイントを解説
- AI
Septeni FOCUS 編集部

生成AIは、画像生成や文章作成、データ分析など、さまざまな分野で活躍する画期的な技術です。しかし、活用の仕方によっては課題やリスクも存在するため、注意が必要です。
この記事では、生成AIのメリットとデメリット、問題点とその対策方法について解説します。
※こちらの記事は2025年3月17日時点の情報です。
生成AIとは

生成AIとは、ジェネレーティブAIとも呼ばれ、膨大なデータを学習して、人間のように新しいコンテンツを生成するAI技術のことです。
従来のAIは、定型業務の自動化がメインの目的であるのに対し、生成AIは与えられた入力(プロンプト)に応じて独自の文章、画像、音声、動画など、クリエイティブなコンテンツを生成できます。
これにより、幅広い分野での生成AI活用が進んでいます。
関連記事:生成AIとは?種類や従来のAIとの違い、活用事例について初心者向けに解説
生成AIが注目される背景

生成AIは、OpenAI社が開発した「ChatGPT」の登場をきっかけに、世界中で広く認知されるようになりました。
企業における作業効率化、クリエイティブ分野の支援など、さまざまな用途で活用されています。
日本では、少子高齢化による労働人口の減少や、働き方改革の推進を背景として、生成AIの普及が進んでいます。
業務効率化や生産性向上、市場競争力強化を目的としたDX(デジタルトランスフォーメーション)の一環としても注目され、多くの企業が生成AIの導入を検討しているのが現状です。
しかし、生成AIの普及が急速に進む一方で、機密情報や個人情報の流出、フェイク画像の生成など、生成AIの問題点が浮き彫りになっているのも事実です。
生成AIを導入する際は、メリットだけでなく、デメリットやリスクも理解したうえで、慎重な検討が必要になるでしょう。
生成AIのメリット

生成AIには多くのメリットがあり、特にビジネス分野においてさまざまな価値を生み出しています。
ここでは、生成AIのメリットについて、具体例を挙げて紹介します。
業務効率化をサポートする
生成AIは定型業務の自動化を実現し、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
例えば、カスタマーサポートにおける問い合わせ対応を自動化することで、従業員はより戦略的な業務や創造的な作業に集中できるようになります。
また、生成AIを活用してECサイトの商品説明文を自動作成すれば、これまで時間がかかっていた商品ページを短時間で作成できるようになり、公開までのリリーススピードも短縮できるでしょう。
生成AIにはさまざまなツールがあるため、自身の目的に応じて選定する必要があります。
アイデアの考案に活用できる
生成AIは、アイデアを生み出すプロセスを効率化し、新しい発想を提供します。
特に、ブレインストーミングや企画書の作成に役立つでしょう。
例えば、商品名の候補を複数出したり、新規プロジェクトのコンセプトを提案するなど、生成AIは異なる視点からアイデアを補完することが可能です。
これにより、より革新的なアイデアが生まれる可能性が高まり、企画書の作成にかかる時間を大きく削減することができます。
クリエイティブの作成ができる
生成AIは、文章だけでなく、画像、動画、音楽など幅広いクリエイティブコンテンツの制作に対応しています。
例えば、ブログ記事やSNS投稿の作成、企業紹介動画の制作やブランドイメージに合ったオリジナル音楽の作曲など、さまざまな用途に活用可能です。
従来手間がかかっていたクリエイティブプロセスを効率化し、ビジネスのスピードと品質を向上できるのも、生成AIの大きなメリットだと言えます。
顧客との関係を強化する
生成AIは、顧客データを分析し、個別のニーズに対応したサービスを提供することができます。
例えば、AIチャットボットを活用すれば、24時間365日いつでも迅速なカスタマーサポートが可能となり、顧客満足度を向上させます。
個々の顧客にパーソナライズされた対応を行うことで、リピーターの獲得にもつながる効果も期待できるでしょう。
データ分析・意思決定を迅速化できる
生成AIのメリットは、膨大なデータを高速で処理できる点にもあります。
市場動向を分析してトレンドを予測したり、競合他社の動向分析にAIを活用することで、タイムリーなビジネス判断ができるようになるでしょう。
企業が迅速に意思決定を行える環境を構築することは、市場競争力の強化に直結する大きなメリットと言えます。
コスト削減につながる
生成AIの活用により、従来人力で行っていた業務を自動化したり、繰り返し必要となる事務作業をAIで効率化すれば、人件費や運用コストの削減につながります。
従業員はより重要な業務に集中できるため、一人ひとりの業務生産性が高まり、全体的なコストパフォーマンスが向上するでしょう。
生成AIのデメリット

生成AIには多くのメリットがある一方で、デメリットやリスクも考慮しなければいけません。
不適切な運用や管理不足によるトラブルを避けるためには、リスクを事前に理解し、適切な対策を講じることが重要です。
続いては、生成AIの主なデメリットと注意点を4つ解説します。
情報漏えいのリスクがある
生成AIツールに顧客の個人情報や企業の機密情報を入力すると、意図せず外部にデータが流出するリスクがあります。
生成AIは、学習のためにデータの収集・処理を行います。入力したデータは外部サーバーに送信されるため、この過程で外部に漏れる可能性が指摘されています。
また、技術的なバグや人為的ミスによってデータが漏洩する危険性も存在するでしょう。
実際に、韓国のサムスン電子では、エンジニアが社外秘であるソースコードをChatGPTに入力し、外部流出させるという問題が発生しています。
この事例は、生成AIを活用する際の慎重な運用の必要性を浮き彫りにし、情報管理やセキュリティ対策の重要性を再認識させるものとなりました。
著作権侵害やフェイクコンテンツ生成の可能性がある
生成AIは、大量の既存データをもとに新しいコンテンツを生成します。
この過程において、知らず知らずのうちに第三者の著作権を侵害したり、既存のデザインや文章と類似性の高いコンテンツを生成してしまう可能性があることに注意が必要です。
また、ディープフェイク技術を使った偽造動画の作成など、意図的に誤解を招くようなフェイクコンテンツの作成も、技術的には可能となっています。
このようなコンテンツをそのまま利用してしまうと、社会的混乱を引き起こしかねず、企業の社会的信用を大きく損なうリスクがあるため、生成されたコンテンツが正しい内容であるか、著作権を侵害していないかなどは必ず人の目で検証する必要があります。
悪用されるリスクがある
生成AIは、その優れた生成能力ゆえに、悪意ある目的で利用される可能性があります。
例えば、詐欺メールの自動生成では、特定の個人情報を引き出すために、リアルな文面をAIが作成し、被害者を欺くといったケースが増えています。
また、ランサムウェアやマルウェアといった有害なプログラムのコードを生成する目的でAIを悪用する例も報告されています。
プロンプトによってアウトプットの質が異なる
生成AIの出力結果は、入力されるプロンプトの質に大きく依存します。
効果的なプロンプトを入力すれば高品質なアウトプットを得られる一方で、曖昧なプロンプトを入力すると、生成された内容が不適切であったり、質の低い結果が出力されることもあるでしょう。
特に初心者が生成AIを活用する場合、適切なプロンプトを作成できず、ツールのポテンシャルを十分に活かせない可能性があります。
また、利用者の知識や経験によって生成物の品質に大きな差が出ることも懸念点の一つです。
生成AIのデメリットや問題点はどう対策する?

生成AIの活用には、情報漏えいや誤情報の生成など、さまざまなリスクを伴います。
しかし、これらの問題は事前に適切な対策を講じることで、軽減することが可能です。
ここからは、生成AIの問題点を対策するための具体的な方法を5つ紹介します。
セキュリティ対策を行う
生成AIのセキュリティ対策としては、主に以下のようなことが挙げられます。
- 信頼性の高いツールの導入
- アクセス権の厳密な管理
- 社内運用ルールの策定
- 監視システムの導入 など
まずは、導入する生成AIツールが、十分なセキュリティや暗号化技術を備えているかを確認することが必要です。信頼できるツールなのか、万が一のときのサポート体制がどのようになっているかも把握しておきましょう。
社内で生成AIを利用する場合、アクセスできる人やデータの範囲を限定することで、不正使用のリスクを最小限に抑えることができます。
個人情報や機密情報は入力しないなど、運用ルールを明確に定めることも重要です。
さらに、サイバー攻撃や不正アクセスを防ぐには、監視システムの導入も検討しましょう。不自然な動作や不適切なコンテンツを早期に検知することで、リスクを最小限に抑えることができます。
人間による検証を行う
生成AIが生成したコンテンツは、必ず人間による検証を行うことが重要です。
著作権・商標権を侵害していないか、適切でない情報が含まれていないかなど、最終的な確認を人間が行うことで、内容の正確性や信頼性を確保しましょう。
特に、外部に公開する資料やデータについては、複数の担当者による二重チェックを行うことをおすすめします。
社内ガイドラインを策定する
生成AIを社内で安全に活用するためには、ガイドラインを策定し、どのようなデータを入力して良いか、生成されたコンテンツをどのように扱うべきかなど、具体的な指針を明確にすると良いでしょう。
また、従業員が生成AIの利便性とリスクを十分に理解し、適切に利用できるよう、定期的な教育やトレーニングを行うことも大切です。
これにより、社内のAIリテラシーが向上し、従業員が統一された基準でツールを利用できるようになります。
プロンプトのテンプレートを用意する
繰り返し利用するプロンプトについては、汎用性の高いテンプレートを作成しておくと効率的です。
テンプレートがあれば、プロンプトの質に左右されることなく、アウトプットの質を標準化させることができます。
時間の経過とともに業務や市場のニーズが変化するため、テンプレートは定期的に見直しを行いましょう。
関連記事:生成AIのプロンプトとは?上手な使い方や指示出しのコツ、8つの例文を紹介
生成AIに関する法律を理解する
法的リスクを最小限に抑えながら生成AIを活用するには、著作権法や個人情報保護法など、関連する法律や規制を理解しておくことも重要です。
また、文化庁が提供するガイドラインや関連団体が発行する資料を参照して最新の規制を把握したり、専門家によるセミナーに参加し、法規制の背景や具体的な対策について学ぶのも良いでしょう。
生成AIのデメリットは対策できる!安全かつ効果的に活用しよう

生成AIは、データ分析などのほかにも、画像やテキスト、動画の作成といったクリエイティブなコンテンツを生成でき、さまざまな分野で活躍する画期的な技術です。
企業で導入することで、業務効率化やクリエイティブなコンテンツの作成を支援するなど、さまざまなメリットが得られます。
生成AIのデメリットやリスクに対しては、セキュリティ対策や社内ガイドラインの整備、プロンプトのテンプレート作成といった対策を講じることで、安全かつ効果的な活用を実現できるでしょう。
生成AIは、企業の持続可能な成長を支える重要な技術です。
リスクを最小限に抑え、その可能性を最大限に引き出すことで、市場競争力の向上や新たなビジネスチャンスの創出につなげていきましょう。
執筆者

Septeni FOCUS 編集部
「Septeni FOCUS」は、Septeni Japan株式会社が運営するマーケティング担当者のためのメディアです。
カテゴリ
関連するお役立ち資料
関連するお役立ち資料はありません。
関連するウェビナー / アーカイブ動画
-

- セミナー
- 開催日 2026.2.12
AI検索面×AI Max!Google広告のポテンシャルを最大化する方法
-
.jpg?width=380&height=222&name=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC_02a_1628x850_B_250528172200CFM139279%20(2).jpg)
- アーカイブ
- 開催日 2025.6.18
2025 Marketing Summit TikTok for Business & セプテーニ 協業セミナー
-

- アーカイブ
- 開催日 2025.2.19
「AIエージェントで変わるマーケティング最前線」 〜海外最新事例と企業導入・活用のリアル〜
-

- アーカイブ
- 開催日 2024.12.19
AIとLINE公式アカウントで実現する顧客体験の革新
-

- アーカイブ
- 開催日 2024.10.03
Performance Marketing Summit Meta & セプテーニ 協業セミナー