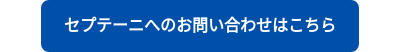AIエージェントとは?生成AIとの違い・簡単な作り方・業務活用事例を分かりやすく解説
- AI
Septeni FOCUS 編集部
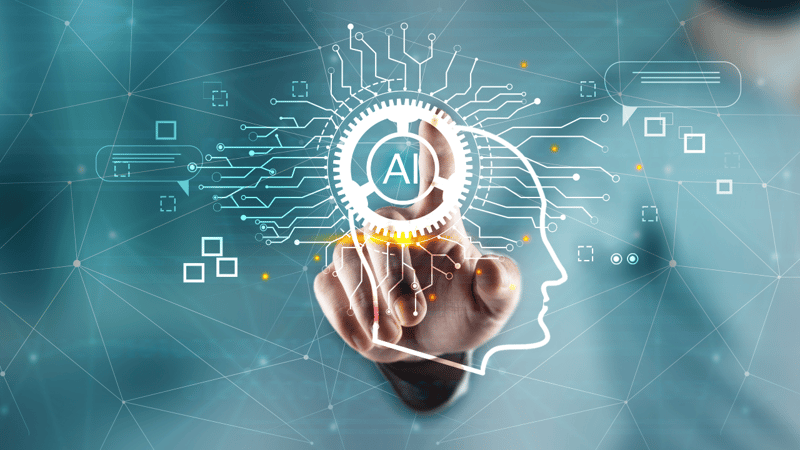
AI技術の進化により、ビジネスや日常生活の中で「AIエージェント」という言葉を目にする機会が増えています。
「AIエージェントって何?」「チャットボットや自動応答と何が違うの?」と、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、AIエージェントの基本的な仕組みや生成AIとの違い、簡単な作り方や活用事例まで、初心者にも分かりやすく解説します。
※こちらの記事は2025年7月24日時点の情報です。
AIエージェントとは

AIエージェントは、ユーザーの目標達成に向けて自律的に計画を立て、必要なタスクを実行するAIです。
人間が細かく指示を出さなくても、AIが状況を判断し、必要な情報を自ら収集して最適なアクションを選択・実行します。
例えば、営業活動の支援や顧客対応、リサーチ業務など、複数の工程が連続する業務でも、AIが全体の流れを把握し状況に応じた対応が可能です。
近年は、生成AIと組み合わせたAIエージェントも登場しており、自然言語によるやり取りを通じて、人間のような応答や判断が可能になっています。AIエージェントはチームの一員として能動的に働く「デジタルアシスタント」のような存在であり、業務効率化や省人化を実現する強力なツールとして注目を集めています。
AIエージェントの特徴
-4.png?width=1280&height=720&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(1)-4.png)
続いては、AIエージェントの主な特徴を解説します。ビジネスに有効活用できるよう、理解を深めていきましょう。
自律性がある
AIエージェントは、自律的に判断・行動できるのが大きな特徴です。あらかじめ設定された目標に対して、人間からの細かい指示を受けることなく、自分で必要な作業を判断し、実行に移します。
例えば、「競合商品の情報をリサーチしておいて」といった曖昧な依頼でも、検索ワードの設定や必要な情報の収集、比較分析や結果の要約といった一連の作業を自動でこなせるのが強みです。人間が行う作業が大幅に削減されるため、業務効率化や生産性向上に大きく貢献します。
環境との対話能力
AIエージェントは、ユーザーの発言やニーズを自然言語で正確に理解し、文脈に応じた柔軟な対話ができます。
Webサイトの情報、外部データベース、APIなどと連携し、リアルタイムで必要な情報を取得・活用することも可能です。
例えば、ユーザーが「今週の天気予報を教えて」と依頼すると、AIエージェントは気象データのAPIにアクセスして最新情報を取得し、分かりやすく要約して返答します。スムーズな対話を実現しつつ、目的達成に向けた情報の取得と活用ができる点は、AIエージェントならではの強みです。
マルチタスク処理
AIエージェントは、複数のタスクを同時進行または順序立てて処理する柔軟性を持っています。
業務プロセスの全体像を把握したうえで、各ステップを自律的に判断し、次のアクションを適切に選択してくれるのが特徴です。
例えば、商品レビューの分析を行う際には、レビュー収集やポジティブ・ネガティブな表現の分類、グラフ化、レポート作成といった工程をすべて自動化できます。
タスク同士の関連性や優先順位を理解して、効率的かつ論理的に業務を遂行してくれるのが特徴です。
学習・改善機能
AIエージェントには、継続的にパフォーマンスを向上させる学習・改善機能が備わっており、過去の対話履歴やユーザーのフィードバックを分析することで、より精度の高い判断や回答が可能です。
例えば、過去に「A社は除外して」と指示された経験を学習すると、今後同様のタスクでは、自動的にA社を対象外として処理するようになります。時間とともにパーソナライズされ、使えば使うほど賢くなるという点は、従来型のAIにはないAIエージェントの魅力です。
外部ツールとの連携
AIエージェントは、Google WorkspaceやSlack、Notion、Outlookなどの各種外部ツールと連携し、業務の自動化を強力にサポートします。
「来週の会議日程を調整して」「関係者にメールして」「カレンダーにも登録して」といった一連の業務を、ワンコマンドで処理することが可能です。
また、顧客データの更新やCRMへの入力作業、社内のナレッジ共有もAIエージェントに任せられるようになります。
ツール操作の煩雑さから解放され、作業ミスの防止や業務スピードの向上にもつながるでしょう。
AIエージェントと生成AIの違い
-3.png?width=1280&height=720&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(2)-3.png)
AIエージェントと生成AIは、どちらも人工知能を活用した技術ですが、目的や役割に違いがあります。
|
項目 |
生成AI |
AIエージェント |
|
主な役割 |
テキスト・画像・音声など、コンテンツを新しく「作る」ことに特化 |
ユーザーの目的達成に向け、タスクを自律的に「実行」する |
|
処理の特徴 |
与えられた指示(プロンプト)に対して単発的に応答する |
状況を判断しながら複数の作業を一貫して進める |
|
主な活用分野 |
コンテンツ生成、文章作成、画像作成など |
情報収集、レポート作成、業務の自動化、ツール連携など |
|
対応の柔軟性 |
基本は一問一答型で、外部環境へのアクションは行わない |
外部ツールやサービスと連携しながら、動的に対応を変える |
|
学習・改善 |
過去データやパターンをもとに生成精度を向上させる |
ユーザーのフィードバックや履歴を取り入れ、行動や応答を賢く進化させる |
|
具体例 |
ChatGPT、Midjourney、DALL-Eなど |
営業支援AI、カスタマーサポートAI、自動レポート作成AIなど |
生成AIは、文章・画像・音声などのコンテンツを新しく生み出すことに特化した技術です。
ChatGPTは自然な文章を生成し、Midjourneyは指示に応じた画像を生成するなど、人間のアイデアや感性を補う「クリエイター型AI」として機能します。
基本的には与えられたプロンプト(指示)に応じて出力を返す、単発的な応答型の動作を行います。
一方、AIエージェントは、与えられた目的を達成することを最優先に、複数のタスクを自律的に処理する「実行型AI」です。
ユーザーから「〇〇を調べてレポートして」といった曖昧な指示を受けても、検索・要約・文書作成・共有まで一貫して行い、場合によっては外部ツールとの連携も自動で実行します。
つまり、生成AIは「作るAI」、AIエージェントは「働くAI」であることが大きな違いです。
さらに最近では、生成AIを内部に組み込んだAIエージェントも増えており、より柔軟かつ知的なアクションが可能になっています。
業務に応じて使い分けることで、作業の自動化や生産性の向上に効果をもたらすでしょう。
関連記事:ChatGPTとは?使い方や活用シーン、無料でできる始め方を紹介
関連記事:Midjourney(ミッドジャーニー)でAI画像生成!料金や使い方、プロンプトを紹介
AIエージェントの活用事例
-3.png?width=1280&height=720&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(3)-3.png)
AIエージェントは、ビジネスのあらゆるシーンで活用されています。
単なる作業自動化にとどまらず、分析・提案・実行までを一貫して担うことで、従来の業務プロセスを大きく変革しています。
ここでは、AIエージェントの代表的な活用事例を3つ紹介します。
ツイート分析
AIエージェントを活用すれば、特定のキーワードやハッシュタグにもとづいて、X(旧Twitter)の投稿を自動で収集・分析できます。
例えば、新商品の評判を把握したい場合、関連する投稿を収集し、ポジティブ・ネガティブの感情分類、投稿ユーザーの属性推定、拡散度の測定などをレポート化することが可能です。
また、炎上リスクが高まっている兆候を自動で検知して、関係者に通知する仕組みも構築できます。
リアルタイムでSNS上の動向を把握できるため、ブランドイメージの維持や迅速なマーケティングにつながるでしょう。
市場調査の自動化
AIエージェントは、Webサイト・ニュース記事・SNS投稿・IR情報・レビューサイトなど、複数の情報源からデータを横断的に収集し、目的に合わせて分析・要約することができます。
具体的には、競合企業の製品価格やユーザーレビュー、業界動向を短時間で集約し、自社向けのレポートとして出力するといった使い方が可能です。自然言語処理や画像認識機能と組み合わせることで、定量データと定性データの両方を解析でき、調査精度の向上にもつながるでしょう。
従来は数日~数週間かかっていた作業が数時間で完了するケースもあり、スピードと情報の網羅性が大幅に向上します。
マーケティングの最適化
AIエージェントは、顧客データや行動履歴の分析、トレンドの把握、広告パフォーマンスのモニタリングなどを自動で行い、マーケティング施策の最適化を支援します。
複数のデータソースをもとにターゲット層を明確に分類し、それぞれに合ったタイミングやチャネル、コンテンツでアプローチすることが可能です。
また、AIエージェントは広告効果のモニタリングやA/Bテストの自動実施も行えます。
成果に応じて施策内容をリアルタイムで調整したり、コンバージョンの高いユーザーにリソースを集中させられるなど、ROIの最大化を支援してくれるでしょう。
カスタマーサポートの効率化
AIエージェントによる、カスタマーサポート業務の自動化も進んでいます。
ユーザーからの問い合わせに対して、24時間365日安定した品質でサポートするだけでなく、AIエージェントなら、よくある質問(FAQ)の提案やトラブルシューティング、契約内容の確認、配送状況の案内といった定型業務にも幅広く対応可能です。
また、自己学習機能を持つAIエージェントは、ユーザーの反応やフィードバックをもとに回答精度を継続的に改善し、より自然で的確な応対ができるようになるでしょう。
さらに、AIエージェントは複雑な問い合わせには有人対応へとスムーズに切り替える「ハイブリッド運用」にも対応しています。
オペレーターの負担を軽減しながらも、対応の品質を損なうことなく運用できる点も大きなメリットです。
最近では、チャットボットだけでなく、音声通話に対応したボイスボットや、LINE・Instagram・X(旧Twitter)などさまざまなチャネルに対応したマルチチャネル型AIエージェントも普及しています。
営業支援・メール作成
営業活動においても、AIエージェントは強力なアシスタントとして機能します。顧客情報や過去のメール履歴、商談フェーズに応じて、提案文書やフォローアップメールを自動で作成・送信することが可能です。営業担当者の業務負担を軽減し、パーソナライズされた高品質なコミュニケーションを実現できる点が評価されています。
さらに、CRMやスケジュール管理ツールと連携すれば、見込み客への最適なアプローチのタイミングを判断し、自動でメール送信を行うといった施策も可能です。
送信後のメール開封率やリンクのクリック状況もリアルタイムでモニタリングされ、反応の良いユーザーへの再アプローチを自動化することで、成約率の向上にもつながります。
会議記録と要約の自動化
AIエージェントは、会議の議事録作成にも活用できます。
ZoomやMicrosoft Teams、Google Meetなどの会議ツールと連携し、内容をリアルタイムで記録・要約し、議事録として自動で作成・共有することが可能です。
さらに、発言を即座に文字起こししたうえで、重要な決定事項やアクション項目を自動で抽出してくれます。
作成した議事録は、SlackやGoogle Drive、社内チャットツールなどに自動で共有できるため、議事録作成にかかる時間を大幅に削減し、情報の抜け漏れや共有ミスを防ぐことにもつながります。
採用業務の効率化
AIエージェントは、人事・採用業務においても非常に有効です。
例えば、求人要件に合致した人材を応募者データから自動で抽出・評価したり、履歴書や職務経歴書の情報をもとにスキル・経験をスコアリングしたりすることで、書類選考を自動化できます。
また、応募者の表情・声のトーン・回答内容を分析して評価に反映する「AI面接」の形でも活用されており、面接官の主観によるバラつきを軽減できるでしょう。
近年では、チャットボットを使った応募者対応も一般的になってきました。
採用プロセスの各段階でAIを取り入れることで、迅速かつ公平な人材選定が可能となり、採用活動全体の効率と精度が大幅に向上します。
AIエージェントの作り方
-2.png?width=1280&height=720&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(4)-2.png)
AIエージェントは、以前のように高度なプログラミングスキルがなければ作れないというものではありません。
現在では、ソースコードが不要なノーコードや、少ないソースコードで作成できるローコードで構築可能なツールやプラットフォームが多数登場しています。
ChatGPTやClaude、Geminiといった生成AIをベースに、自社の業務ニーズに合わせたAIエージェントを手軽に開発・導入できる環境が整いつつあると言えるでしょう。
ここでは、AIエージェントを作るための基本ステップを5つに分けて紹介します。
1. 目的と役割を明確にする
まずは、「営業支援」「カスタマーサポート」「レポート作成」など、どの業務を自動化・効率化したいのかを具体的に決めることが大切です。AIエージェントの利用目的が明確になれば、必要な機能や設計方針にブレが生じにくくなります。
また、社内利用なのか、顧客向けなのかといった想定ユーザーも定めておくことで、より実用性の高いエージェント設計が可能になるでしょう。AIエージェント開発の成否を分ける最も重要なステップです。
2. 使用するAIモデルを選定する
次に、目的に適したAIモデルを選定します。
目的や用途に応じて「対話重視型」「検索連携型」「データ処理特化型」といったAIの機能特性も考慮すると、より効果的な設計が可能です。
|
AIモデル |
提供会社 |
機能特性 |
|
OpenAI |
・自然な対話、柔軟な応答、記憶機能を活かした継続的なコミュニケーションが強み |
|
|
Anthropic |
・長文の読解や要約、丁寧な対話表現に優れている |
|
|
|
・Google検索との統合やリアルタイムデータの取得が強み |
選定したモデルが提供するAPIやノーコードツールを使うことで、開発のハードルも大きく下がります。
3. プロンプトや指示文を設計する
AIエージェントの精度を左右するのが、プロンプト(指示文)の設計です。
例えば、「営業用のフォローメールを作成して」とだけ指示するのではなく、「過去のやり取りを踏まえて」「丁寧語で」「200文字以内」など、具体的な条件を加えることで、より期待に近いアウトプットが得られます。
初期段階では思い通りの動作をしないことも多いため、テスト→調整→再テストを繰り返しながら、徐々にプロンプトを最適化するのがポイントです。この工程は「プロンプトエンジニアリング」と呼ばれ、近年ではビジネススキルの一つとしても注目されています。
4. 外部ツール・APIと連携する
AIエージェントを実際の業務に組み込む際は、ほかのツールとの連携設計も重要です。
例えば、Slack、Googleカレンダー、CRMツール、Googleスプレッドシートなどと接続することで、AIに「情報収集→処理→共有」までを一気通貫で実行させることができます。
また、CRMやSFAツールと連携すれば、見込み顧客へのアプローチメールの自動送信や、フォローアップのスケジューリング、商談進捗の自動記録といった「営業活動の自動化」を実現できるでしょう。
営業担当者の手間を減らし、提案・商談など本来注力すべき業務に集中できる環境が整います。
さらに、ノーコードツールを使えば、プログラミング技術がなくても、外部ツールとの連携が設定可能です。
プログラミング技術があれば、独自のAPIや社内システムと接続し、より柔軟で高機能なエージェントを構築することもできます。
5. テストと改善を繰り返す
作成したAIエージェントは、実際の利用シーンでテストを行い、継続的に改善していくことが不可欠です。 どれだけ設計が優れていても、実際の運用環境では予期せぬ応答やタスク漏れが発生することがあります。
そのため、プロンプトや条件設定の見直し、連携処理のチューニング、ユーザーからのフィードバック反映などを繰り返しながら精度を高めていきましょう。
ノーコードプラットフォームの多くでは、出力ログの確認やA/Bテスト機能、パフォーマンスの可視化ツールなどが用意されており、こうした仕組みを活用することで改善サイクルを効率化できます。
AIエージェントは「作って終わり」ではなく、「運用しながら育てていく」ことで、真の価値を発揮します。運用開始後も柔軟に改善を続ける体制を整えておくことが、成功のカギとなるでしょう。
AIエージェントで業務の自動化・最適化を実現しよう
-1.png?width=1280&height=720&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(5)-1.png)
AIエージェントは、ただのチャットボットや生成AIとは異なり、「自律的に考え、行動し、学習する」実務型のAIです。
単発的な応答や生成にとどまらず、業務フローを理解したうえで複数のタスクを一貫して実行する力を持っており、企業の生産性向上や業務の効率化に大きく貢献します。
すでに開発・提供されているAIエージェントサービスを導入する方法もありますが、近年ではノーコードやローコード開発環境の進化により、専門的な知識がなくても自社ニーズに合ったAIエージェントを柔軟に設計・構築することが可能になっています。
今後、AIエージェントはビジネスにおける「新しいチームメンバー」として、欠かせない存在になっていくことが期待されます。
まずは小さなタスクからでもAIエージェントで自動化し、その利便性を実感してみてはいかがでしょうか。
執筆者

Septeni FOCUS 編集部
「Septeni FOCUS」は、Septeni Japan株式会社が運営するマーケティング担当者のためのメディアです。
カテゴリ
関連するお役立ち資料
関連するお役立ち資料はありません。
関連するウェビナー / アーカイブ動画
-

- セミナー
- 開催日 2026.2.12
AI検索面×AI Max!Google広告のポテンシャルを最大化する方法
-
.jpg?width=380&height=222&name=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC_02a_1628x850_B_250528172200CFM139279%20(2).jpg)
- アーカイブ
- 開催日 2025.6.18
2025 Marketing Summit TikTok for Business & セプテーニ 協業セミナー
-

- アーカイブ
- 開催日 2025.2.19
「AIエージェントで変わるマーケティング最前線」 〜海外最新事例と企業導入・活用のリアル〜
-

- アーカイブ
- 開催日 2024.12.19
AIとLINE公式アカウントで実現する顧客体験の革新
-

- アーカイブ
- 開催日 2024.10.03
Performance Marketing Summit Meta & セプテーニ 協業セミナー