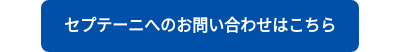ChatGPTの情報漏えいリスクとは?企業を守るセキュリティ対策について解説
- AI
Septeni Focus 編集部

ChatGPTなどの生成AIは、業務効率化や創造性の向上に大きな可能性をもたらしています。
一方で、ChatGPTの利用には情報漏えいのリスクも伴うため、適切な管理が必要です。
この記事では、ChatGPTの情報漏えいに関するリスクと対策について、具体例を挙げて分かりやすく解説します。
※こちらの記事は2025年3月17日時点の情報です。
ChatGPTで情報漏えいが懸念される理由
.jpg?width=1280&height=720&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(13).jpg)
ChatGPTでの情報漏えいが懸念される理由としては、以下の3つが挙げられます。
- 学習データの蓄積
- 外部サーバーへデータ保管
- システムのバグや不具合
ChatGPTは、ユーザーが入力した情報をデータベースに蓄積し、学習材料として活用します。
過去のユーザーが入力した情報が学習データとして反映される場合もあり、機密情報や個人情報を入力すると、その情報が意図しない形で出力されることもあるでしょう。
また、ChatGPTは外部サーバーにデータを保管しているため、サーバーの不正アクセスやハッキングによって情報が流出する危険性もあります。
さらに、システムのバグや不具合によって、ほかのユーザーに機密情報が漏えいしてしまうリスクもあり、予期せぬエラーや脆弱性を狙った攻撃を完全に防ぐのは、非常に難しいのが現状です。
関連記事:ChatGPTとは?使い方や活用シーン、無料でできる始め方を紹介
ChatGPTの情報漏えいの事例
.jpg?width=1280&height=720&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(14).jpg)
ChatGPTを提供しているOpenAI社は、2023年3月に「一部ユーザーの個人情報が流出した」と発表しました。
アクセス制御が正しく機能しておらず、一部のユーザーに対して、ほかのユーザーのチャット履歴や決済情報が開示されてしまうというバグが発生し、個人情報が漏えいしたのです。
この事例を受けて、生成AIの利用におけるセキュリティ対策の重要性が広く認識されるようになりました。
ChatGPTの利用を規制したり、社内ルールの見直しを行う企業の動きも見られています。
ChatGPTで注意したいセキュリティリスク
.jpg?width=1280&height=720&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(15).jpg)
ChatGPTで注意すべきセキュリティリスクは、情報漏えいだけではありません。
以下の3つのリスクも理解し、適切に対策を講じることが重要です。
著作権・プライバシー
ChatGPTが生成するコンテンツの著作権は原則として利用者に帰属するため、商用利用も可能です。
しかし、ChatGPTの生成物については、意図せず他人の著作権やプライバシーを侵害するリスクがあります。
ChatGPTはユーザーが入力した情報やインターネット上の膨大なデータを学習するため、生成された文章や画像が、すでに公開されている既存の著作物と似てしまう可能性はゼロではありません。
そのため、ChatGPTの成果物を利用する際は、プロンプトに個人情報が含まれていないか、成果物と類似の著作物がないかをしっかりと確認して、侵害を防ぐことが重要です。
誤った情報・フェイクニュース
ChatGPTの生成物は、正確性が保証されているわけではありません。
学習データをもとに回答を生成するため、情報が古かったり、誤りが含まれていたりする場合があります。
そのため、ChatGPTの生成物をそのまま公開すると、誤情報を拡散してしまったり、フェイクニュースと受け取られるリスクがあります。
特に、ニュース記事や調査レポートなどを作成する際は、内容を必ず人間が精査し、正確性や情報の信憑性を確認しましょう。
サイバー攻撃への悪用
ChatGPTの高性能な生成能力は、悪意ある目的にも利用されるリスクがあります。
例えば、ChatGPTを利用して説得力のあるフィッシングメールを作成したり、高度なマルウェアを生成することも技術的には可能です。
これにより、従来のセキュリティ対策では検出が困難な手口が増える可能性が高まり、被害を受けるリスクが増加してしまいます。
企業としては、定期的な社員教育やシステム監視、セキュリティツールの導入など、包括的なセキュリティ対策の強化が求められるでしょう。
ChatGPTをビジネス活用する際のセキュリティ対策
.jpg?width=1280&height=720&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(16).jpg)
ChatGPTをビジネスで安全に活用するためには、セキュリティリスクをしっかりと理解し、適切な対策を講じることが重要です。
ここでは、企業がChatGPTを導入する際のセキュリティ対策について分かりやすく紹介します。
ガイドライン・ルールを策定する
企業がChatGPTを導入する際は、まずは社内で明確なガイドラインやルールを作成し、従業員全員に周知することが必要です。
利用目的や範囲をあらかじめ定めておけば、意図しない使用や情報漏えいのリスクを未然に防ぐことができます。
また、従業員がChatGPTのリスクを正しく理解するために、セキュリティ意識を高める教育を行うことも重要です。
実際のトラブル事例を交えた具体的な研修で、社員の理解を深めましょう。
従業員一人ひとりが安全な使い方を心がけることが、リスク低減への第一歩です。
機密情報や個人情報を入力しない
ChatGPTに入力した情報が学習に利用される可能性があることを踏まえ、機密情報や個人情報を入力しないことも重要です。
例えば、顧客の氏名や住所、未公開のプロジェクトデータなどは入力を避け、入力後に履歴が残らないよう、定期的にデータの削除を行うとより安全です。
また、ChatGPTには「オプトアウト機能」という設定があり、入力データを学習に使用しないよう指定することができます。
OpenAIの公式サイトから申請するか、ChatGPTの設定画面から有効化できるため、活用するのもリスク対策の一つです。
ただし、オプトアウトを利用すると過去のチャット履歴が確認できなくなるデメリットもあるため、自社の業務内容や必要性を考慮して検討しましょう。
API連携を活用する
ChatGPTと自社システムをAPI連携させることで、セキュリティリスクを最小限に抑えることが可能です。
API経由で送信されたデータは、AIの学習には使用されません。
また、API連携により、業務プロセスを効率化しながら、データ管理を一元化できます。
パスワードは定期的に更新する
ChatGPTのアカウント管理において、パスワードの安全性を確保することは基本中の基本です。
アカウント登録時に強力なパスワードを設定するだけでなく、定期的に更新することで不正アクセスのリスクを低減できます。
特に、複数のアカウントを管理している場合は、パスワードの共有や使い回しを避けるよう注意が必要です。
また、パスワード管理ツールを活用することで、セキュリティレベルをさらに向上させることができます。
セキュリティが万全なツールを利用する
ChatGPTを業務に利用する際には、信頼性の高いセキュリティ対策が施されたツールを選ぶこともポイントです。
現在では、ChatGPTの機能をビジネス向けに強化し、セキュリティを重視したAIツールも開発されています。
そういったツールはセキュアな環境で生成AIを活用でき、適切なガイドラインを整備していることも多いため、権利・プライバシー侵害やサイバー攻撃による情報漏えいのリスクを低減できます。
ChatGPTのセキュリティ対策を徹底して情報漏えいを防ごう
.jpg?width=1280&height=720&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(17).jpg)
ChatGPTは、非常に高い言語処理能力やテキスト・画像生成機能を備えており、顧客対応、マーケティング資料の作成、または社内文書の効率化など、幅広いビジネスシーンで活用されています。
しかし、その便利さの一方で、情報漏えいなどのセキュリティリスクについても十分に理解し、対策を講じることが重要です。
ChatGPT以外の信頼性の高いツールの利用も検討しながら、安全に生成AIを活用しましょう。
執筆者

Septeni Focus 編集部
「Septeni FOCUS」は、Septeni Japan株式会社が運営するマーケティング担当者のためのメディアです。