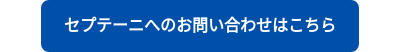AIO(AI検索最適化)とは?対策方法やSEOとの違いを解説
- SEO
- AIO
Septeni FOCUS 編集部

AIの普及により、検索のあり方が大きく変化しつつあります。
これまで主流だったSEO(検索エンジン最適化)に加え、近年、AIによる検索結果を意識した「AIO(AI検索最適化)」という新しい考え方が注目されています。
AIOとは、ChatGPTやPerplexityなどの生成AIがユーザーの質問に答える際、自社コンテンツを適切に引用・要約してもらうための最適化の手法です。
AIがどのように情報を理解し、どんな要素を評価して回答を生成するのかを意識することが重要となります。
この記事では、AIOの基本的な仕組みやSEOとの違い、これからの時代に必要なAIO対策のポイントを分かりやすく解説します。
※こちらの記事は2025年11月7日時点での情報です。
AIO(AI検索最適化)とは

AIO(AI検索最適化)とは、ChatGPTやPerplexity、GoogleのAI Overviewsなど、AI検索エンジンが回答を生成する際に、自社サイトの情報を正確かつ有利に引用してもらうための最適化手法です。
自社のブログや記事がGoogleのAI Overviewsで引用されれば、ユーザーがサイトを訪問しなくても企業名やサービス内容を自然に認知してもらえる効果が期待できます。
AIOとよく似た概念に「GEO(生成エンジン最適化)」や「LLMO(大規模言語モデル最適化)」があります。
GEOは生成AI全般に対して情報を最適化する包括的な考え方であり、AIOやLLMOはその一部として位置づけられます。
AIOとLLMOの違いは、以下の通りです。
|
用語 |
主な対象 |
目的 |
|
AIO (AI検索最適化) |
AI型検索ツール (GoogleのAI OverviewsやPerplexityなど) |
自社コンテンツがAIに正確に理解され、検索結果やAI概要に優先的に引用・表示されるようにする |
|
LLMO (大規模言語モデル最適化) |
ChatGPTやGeminiなどのLLM(大規模言語モデル) |
AIが対話型の回答を生成する際に情報源として正しく参照、引用してもらう |
いずれも「生成AI」を対象としていますが、AIOは「AIによる検索結果の表示(AI Overviewsなど)での引用」を主な目的としているのが特徴です。
AIO(AI検索最適化)が注目されるようになった背景

生成AIの普及に伴い、ユーザーの検索行動はこの数年で大きく変わってきました。
ChatGPTやGeminiなどの生成AIや、PerplexityのようなAI検索ツールが広く使われるようになり、「キーワードを入力し、検索結果から必要な情報を探す」という従来の検索スタイルよりも、「AIに必要な情報を集めてもらう」というアプローチを取るユーザーが増えています。
また、最近ではGoogleのAI Overviewsや、生成AIの回答だけで情報を得る「ゼロクリック検索」が急速に広がり、AIが回答を生成する際にどのサイトを情報源として選ぶかが、アクセス数やブランド認知に直結するようになりました。
このような変化を背景に、多くの企業やウェブサイト運営者は、AIが要約・引用する検索結果を見据えたAIO(AI検索最適化)に積極的に取り組み始めています。
今後の検索対策を考えるうえでは、単に「クリック数を増やす」という視点だけでなく、「AIに選ばれる」ことを目的とした情報設計がカギになってくるでしょう。
企業がAIO(AI検索最適化)対策に力を入れるべき理由

AIO(AI検索最適化)は一過性のトレンドではなく、企業のデジタルマーケティング戦略を根底から変える可能性を持つ新しい検索最適化の考え方です。
続いては、企業がAIO対策に力を入れるべき理由について、最新の市場動向とともに詳しく解説します。
AI検索の利用者が急増
総務省が2025年(令和7年)3月に公表した「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究の請負成果報告書」によると、日本国内における個人の生成AI利用経験率は26.7%に達しています。
特に20代では44.7%と高い水準を示し、生成AIの利用が急速に広がっていることが分かります。


出典:総務省「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究の請負成果報告書」
また、企業でもAIやチャットボットを業務に導入する動きが加速しており、生成AI活用方針を策定している企業は約50%にのぼります。

出典:総務省「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究の請負成果報告書」
さらに、株式会社サイバーエージェントが公表した調査結果によると、日常の検索行動における生成AI利用率は21.3%、10代ではChatGPT(42.9%)がYahoo!JAPAN(31.7%)を上回る利用率となりました。
出典:株式会社サイバーエージェント「サイバーエージェントGEOラボ、生成AIのユーザー利用実態調査を実施」
個人だけでなく企業レベルでも検索・情報活用の中心がAIへとシフトしていくなか、PerplexityやGensparkといったAI型検索ツールも次々に登場しています。
AI検索の利用者は今後も急速に増えていくことが予想されており、企業のブランディングや認知度向上にAIO対策は欠かせないものとなっていくでしょう。
利用者からの信頼度が向上する
ユーザーの検索行動がAIにシフトしつつある昨今、「AIから引用される情報=信頼性が高い」と認識されやすくなっています。
そのため、AIO対策によってAIに正確に理解・引用されるようにすることは、自社ブランドの信頼性や専門性を高めるうえでメリットが大きいです。
特にBtoB領域や医療、金融など信頼性が重視される業界では、AIに引用されること自体が一種の権威づけとして作用します。これにより、ブランドイメージの向上や潜在顧客へのアプローチといった効果が期待できるでしょう。
早く始めるほど有利になる
AIO対策は発展途上の分野ですが、導入を検討する企業も増えてきています。
AI検索エンジンは、回答を生成する際に過去の引用実績や情報源の信頼性を考慮する傾向があります。
そのため、一度「信頼できる情報源」として認識されたサイトは、今後の回答でも継続的に参照・引用されやすくなります。
できるだけ早く最適化をスタートし、AIが参照する定番の情報源としてのポジションを確立できれば、将来的な優位性につながりやすいです。
SEOだけでは不十分
これまで多くの企業が重視してきたSEO(検索エンジン最適化)は、依然として重要な施策ですが、AI時代にはそれだけでは不十分です。
SEOは主に「検索エンジンのアルゴリズム」に合わせて上位表示を狙うのに対し、AIOは「AIが理解しやすい構造や文脈」を重視します。
そのため、SEOをやっていればAIOでも優位に立てるというわけではありません。
これからの検索マーケティングで成功するには、SEOだけに頼るのではなく、SEO+AIOのハイブリッド戦略を構築することが重要になるでしょう。
AIO(AI検索最適化)とSEOの違いと共通点

SEOだけでは不十分とはいえ、現在も多くのユーザーがGoogleなどの検索エンジンを使って情報を得ています。
そのため、SEOを完全にやめる必要はありません。
むしろ、SEOで培った知見や評価をAIOに応用することが、今後の検索対策で大きな強みになります。
AIO(AI検索最適化)とSEOは目的もアルゴリズムも異なりますが、どちらもユーザーに価値ある情報を届けることが根本にあります。
2つの違いを理解し、自社のビジネスモデルや情報発信の目的に応じて戦略を組み合わせることが重要です。
|
項目 |
AIO(AI検索最適化) |
SEO(検索エンジン最適化) |
|
目的 |
AI検索の回答やAI要約(AI Overviewsなど)に自社情報を引用・掲載させる |
GoogleやYahoo!などの検索結果で、自社ページを上位表示させる |
|
施策のポイント |
・AIが理解しやすい構成にする(結論ファースト、FAQ形式など) ・一次情報や出典を明示する ・AIが正確に要約しやすい文体を心がける |
・検索エンジンが評価しやすい構成にする(キーワード最適化、内部リンク、被リンクなど) ・ユーザーの検索意図を満たす網羅的な内容にする |
|
評価のポイント |
・AIが自社情報を引用した回数 ・AI回答への登場頻度 ・AI要約における引用精度 |
・検索順位 ・オーガニック流入数 ・クリック率(CTR) など |
|
期待する効果 |
ゼロクリック検索における露出を増やし、AI経由の信頼・認知を獲得する |
検索結果からのアクセス増加により、CV(コンバージョン)率やブランド認知を向上させる |
ここでは、AIOとSEOの違いや共通点、優先度について詳しく解説します。
AIOとSEOの違い
SEOは検索エンジン上で自社サイトを上位表示させ、ユーザーのアクセスを増やすことを目的としています。
一方、AIOはAIが生成する回答(GoogleのAI OverviewsやPerplexityなど)に自社情報を正確に引用させることが目的です。
そのため、SEOでは「ユーザーの検索ニーズを満たす構成」が求められるのに対し、AIOでは「AIが理解しやすい構成や自然言語での明確な主張」が求められます。
例えば、FAQ形式で質問と回答をセットで提供したり、出典や統計データを明記することは、AIO対策において効果的です。
また、AIは曖昧な表現や過剰に飾り立てた言葉を理解しにくいため、短く簡潔で事実にもとづいた文章構成がAIO対策の基本となります。
AIOとSEOの共通点
AIOとSEOはアプローチが異なるものの、どちらも「ユーザーにとって有益で信頼性の高い情報を提供する」ことを目的としており、根本にある理念は共通しています。
そのため、SEOで重要視されるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の考え方は、AIが情報を評価する際にも強く影響するでしょう。
例えば、専門家による実体験を含む一次情報、透明性のある出典、正確な引用表現などは、AIが「信頼できる情報源」と判断する要素となります。
さらに、AIOとSEOのどちらにも共通するのが「構造化データ(Schema.org)」の活用です。
FAQスキーマやHowToスキーマを正しく設定しておくことで、AIはページ構造を理解しやすくなり、回答に引用される確率が高まるでしょう。
AIOのほうがSEOよりも重要?
AI検索が主流になりつつある今、「AIOがSEOを超えるのでは?」という見方も出ています。
しかし、Google検索からの流入は依然として主要なトラフィック源であり、SEOを軽視するのはリスクと言わざるを得ません。
理想的なのは、SEOで上位表示を狙いながら、同時にAIOによってAIの回答にも引用されるように設計するハイブリッド戦略です。
Google検索で1位を取れなくても、AI Overviewsで引用されれば同等以上の露出効果が得られる可能性があります。
今後AIが検索結果の主要インターフェースになることを踏まえると、「SEOで見つけてもらい、AIOで選ばれる」構造が、これからのデジタルマーケティングにおける理想的な組み合わせと言えるでしょう。
AIO(AI検索最適化)対策の具体的なやり方とポイント

続いては、AIO(AI検索最適化)の具体的なやり方と注意すべきポイントを解説します。
AIが情報を「どう読み取り、どう回答文に引用するか」を前提に考えることが重要なポイントです。
検索意図に沿った分かりやすい構成
AIO対策の第一歩は、「ユーザーの検索意図を的確に満たす構成」を意識することです。
AIはユーザーの質問に即答できる明快な情報を好みます。
特に、質問形式と回答をセットにしたFAQなどはAIに理解されやすく、引用されやすい形式の一つです。
また、リード文や見出しで最初に結論を提示する「結論ファースト型」の構成にすることで、AIが要点を素早く把握しやすくなるでしょう。
検索意図を満たす回答は短く明確に
AIは長い文章や複雑な言い回しを苦手とします。
そのため、AIOでは以下の点を意識することが大切です。
-
一文を短くする(一文一意を心がける)
-
主語と述語を明確にする
-
曖昧な指示詞(これ、それ、あれ)の使用を避ける
-
専門用語や略語には注釈を加える
このように簡潔で分かりやすい表現は、AIが情報の意味を誤解するリスクを減らし、回答に引用されやすくなります。
構造化データの実装
AIにページの意味を正確に伝えるためには、「構造化データ(Structured Data)」の実装が効果的です。
Schema.orgのマークアップを活用し、「FAQ」「HowTo」「Organization」などの構造タイプをHTML内で明示しましょう。
AIに「これは〇〇に関する情報です」と正しく認識させることで、回答に引用・参照してもらえやすくなります。
情報の信頼性・権威性の向上
AIは「信頼できる一次情報」を優先的に引用します。
そのため、以下のような信頼性を高める施策を取り入れることが重要です。
-
一次情報を提示する(自社データ、独自調査、事例など)
-
信頼できる引用元を明記する(政府機関・公的データ・専門団体など)
-
専門家や有資格者の監修をつける
例えば、自社で実施した独自のアンケート結果や分析レポートなどは、他サイトとの差別化にもつながります。
AIは一次情報を独自性の高いコンテンツと判断しやすいため、積極的に取り入れるのがおすすめです。
サイト構造やHTMLタグを整える
AIがサイト内の情報を効率的に収集・理解できるよう、サイト構造やHTMLタグを最適化することも重要です。
これはクローラビリティ(AIや検索エンジンの巡回しやすさ)の向上につながり、SEOと共通する技術的な施策です。
具体的には、以下の点を整備しましょう。
-
サイトマップの送信・更新:サイト全体の構造をAIに正確に伝える
-
見出しタグ(H1・H2など)の適切な使用:コンテンツの階層構造を正しく設定し、情報の重要度を伝える
-
内部リンクの最適化:関連性の高いページ同士をつなぎ、文脈の理解を助ける
引用されやすい表現・要約を意識する
AIに引用されやすいコンテンツには共通した特徴があります。
-
質問と回答を並べた「FAQ形式」
-
見出し下に要点をまとめた「要約文」
-
記事冒頭で結論を提示する「結論ファースト構成」
逆に、前置きが長すぎるストーリー型の文章や、感情表現を多用したコラムはAIには不向きです。
AIは最短で正確な答えを好むため、「情報の本質を短く構造的に伝えること」が、AIOの基本となります。
このようなポイントを意識してコンテンツを作成すれば、AI検索での引用機会が増えるだけでなく、ユーザーにとっても分かりやすい記事になるため、結果としてSEO評価の向上も期待できます。
AI時代を見据えてAIO対策を始めよう

「ググる」という言葉が広まってから20年以上が経ち、今や検索のあり方は大きな転換点を迎えています。
ChatGPTやGeminiといった生成AI、PerplexityのようなAI型検索ツールを通じて、検索結果をクリックせずに答えを得る「ゼロクリック検索」が急速に増えています。
このような変化に伴い、従来のSEO(検索エンジン最適化)だけでは、自社コンテンツの露出や流入確保を十分に担えない可能性が高まってきました。
そこで重要なのが、AIから「信頼できる情報源」として認識され、引用されることを目指すAIOです。
SEOの知見を活かしつつ、AIが理解しやすい構造化データ、文脈を意識したコンテンツ設計、FAQ形式や結論ファーストの構成などを取り入れることで、AIに選ばれるコンテンツ制作が実現できます。
AI主導の検索環境が定着する今、ブランド認知やユーザーからの信頼を維持・拡大するためには、SEOとAIOを両立させる戦略が不可欠です。
AIが何を重視するかを理解し、それに応じたコンテンツを設計することが、これからのAI時代を勝ち残るカギとなるでしょう。
執筆者

Septeni FOCUS 編集部
「Septeni FOCUS」は、Septeni Japan株式会社が運営するマーケティング担当者のためのメディアです。
カテゴリ
関連するお役立ち資料
関連するお役立ち資料はありません。